こんな人のための記事です。
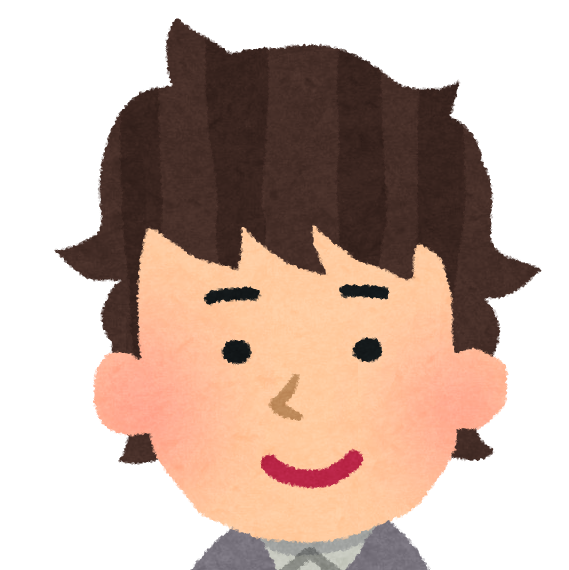
一級建築士の資格が必要だけど、何から手をつけたらいいかわからない。
一級建築士試験は、学科試験が計画、環境設備、法規、構造、施工と5科目もあって、ボリュームが多すぎてどこから手をつけたらいいか迷いますよね。
一級建築士の私がそんな悩みにお応えします。
勉強する手順
結論からまとめると以下のとおりです。
- 学習する科目の優先順位をつける
- 過去問題集を繰り返し解く
- 点数が取りにくい分野をテキストで学習する
- 模試に2、3回挑戦する
順を追って解説していきます。
1. 学習する科目の優先順位をつける
これは基礎の下地ができていない人向けの内容なので、建築の実務経験がある人は2番目以降まで読み飛ばしてください。
これまで設計実務をやったことがない人(一級建築士受験資格のある建築学生を含みます)は、まずは法規から学習を進めることをおすすめします。
理由は以下のとおりです。
- 5科目のなかで配点が高く、高得点を狙いやすい
- 法令集の引き方に慣れる必要がある
- 出題される問題がある程度パターン化されている
法規の試験は30問の4つの選択肢問題になっています。試験時間は1時間45分です。法令集の持ち込みが可能なので時間をかければ基本的に誰でも満点を取れます。
時間制限があるのでいかに効率よく問題を解いていくかがポイントになります。慣れてしまえば回答も早くなり確実に高得点を狙えますが、慣れるまである程度時間がかかります。
時間がかかるものは最初にやってしまいましょう。
法規以降の学習する順番としては、
- 法規
- 構造、施工
- 環境・設備
- 計画
の順がおすすめです。
2. 過去問題集を繰り返し解く
結論からいうと、過去問を完璧にマスターすれば十分合格圏内に入ります。
これは「一級建築士合格支援サイト 合格物語」というサイトで確認することができます。
ただし、過去問の類似問題や応用問題を含んでいるため注意が必要です。過去問の答えを丸暗記すればOK、とはいかないようになっています。
1回目で解ける問題もあれば2回目、3回目とつまづく問題も出てきますが、点数を気にせずにひたすら解きましょう。
3. 点数が取りにくい分野をテキストで学習する
過去問をひととおり解き終わったら、解けなかった問題に関する分野をテキストで確認しましょう。
問題集の解説書はピンポイントの解答しかしてくれません。
一方、テキストはその分野の重要なポイントをしっかり解説しており、問題の応用力が養われるのでおすすめです。
4. 模試に2、3回挑戦する
各科目の学習がひととおり終わったら、模試で腕試しをしてみましょう。
最低でも2回、理想は3回は受けたほうがよいです。というのは2回はやらないと学習の成果がつかみづらいのと、3回受けると試験の平均得点率が見えてくるからです。
初受験の人であれば、問題を解く時間配分に面食らうと思います。
過去問を解いていた時よりもひどい点数を取ってしまった、得意科目が思っていたより点数が取れなかった、なんてこともあります。
実際、私が最初に受けた模試も散々な結果でした。
でも、ここで模試の結果をそのままにして放置してはいけません!
できなかった問題の復習って、気持ちが落ち込むし5科目を一度にやるから量が多くて面倒な作業なんです。
その気持ち、すごくわかります。
でも、ここで諦めずにきちんと復習すれば確実に点数が取れるようになっていきます。頑張りましょう。
まとめ
勉強する手順は以下のとおりです。
- 学習する科目の優先順位をつける
- 過去問題集を繰り返し解く
- 点数が取りにくい分野をテキストで学習する
- 模試に2、3回挑戦する
これらの学習サイクルを習慣化すれば合格への一歩が近づきます。
ぜひ参考にしてみてください。



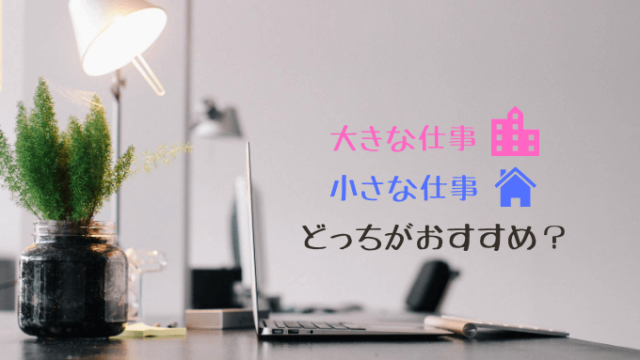
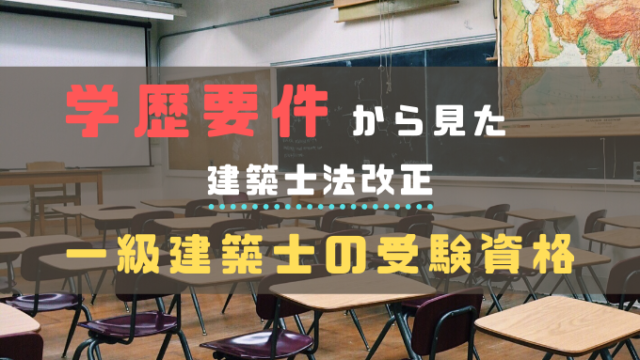

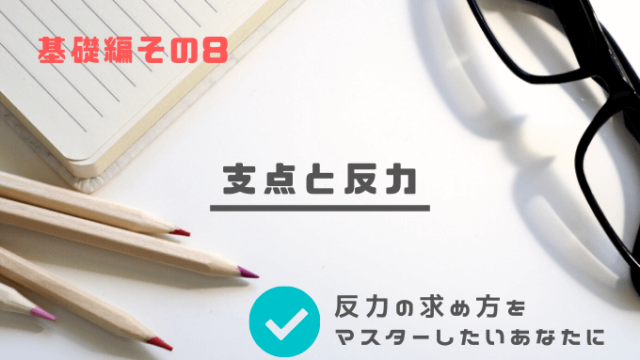

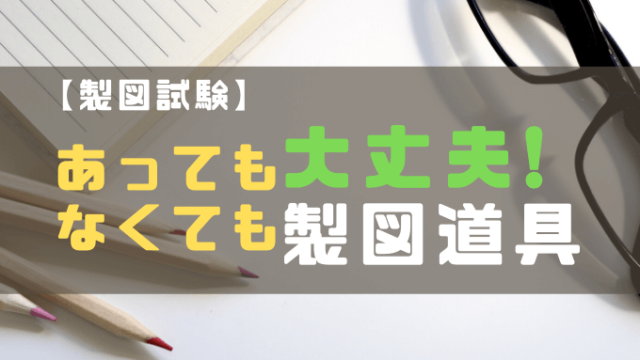

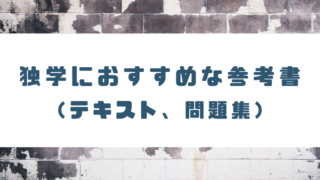


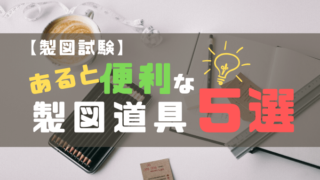


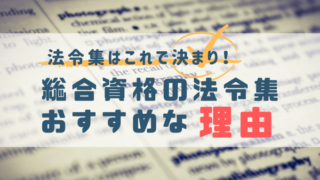




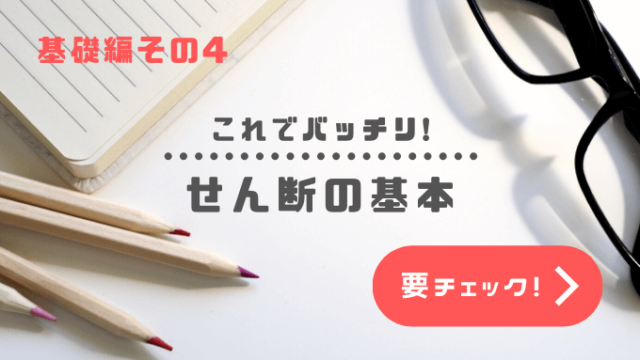
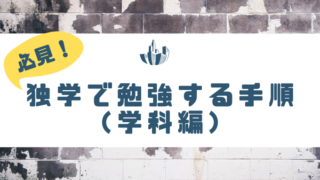
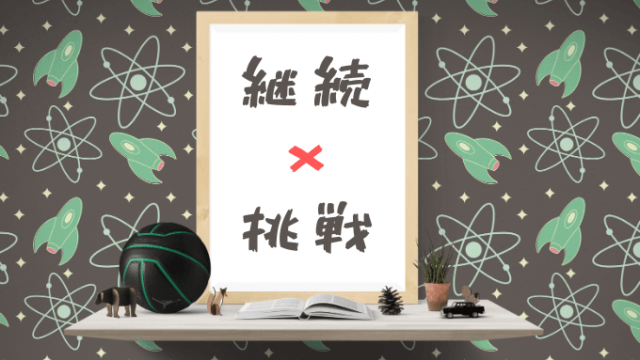
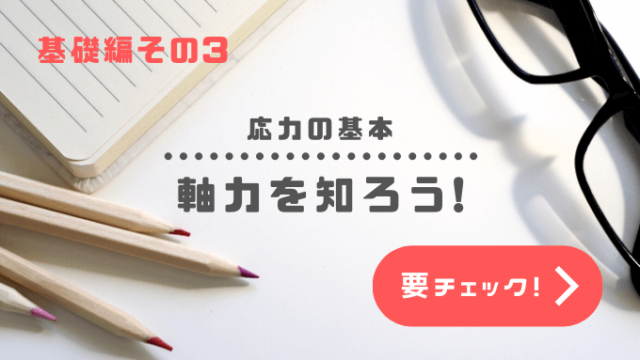



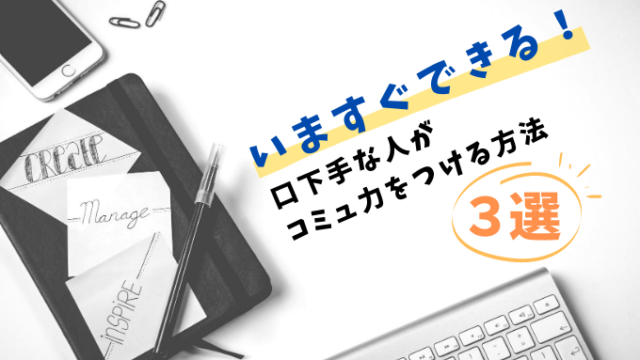

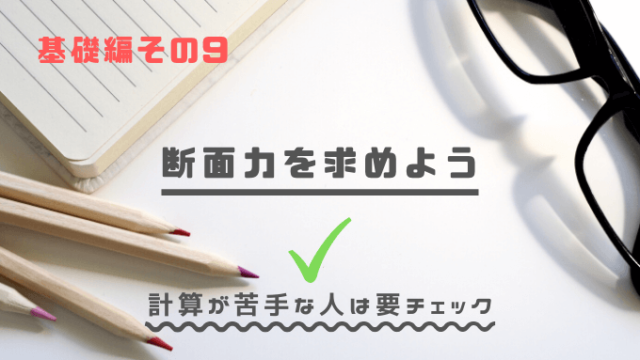
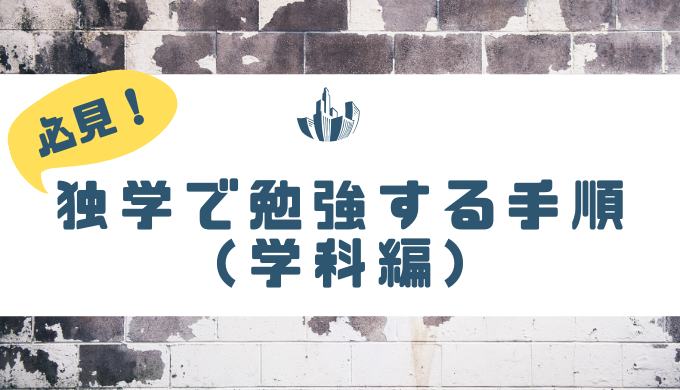
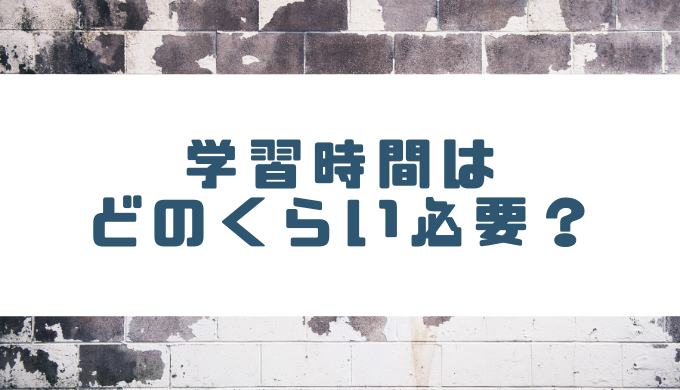
コメント