こんにちは、ゆるカピです。
今回は一級建築士の受験資格が見直されて、求められる実務経験がどう変わったか解説していきます。
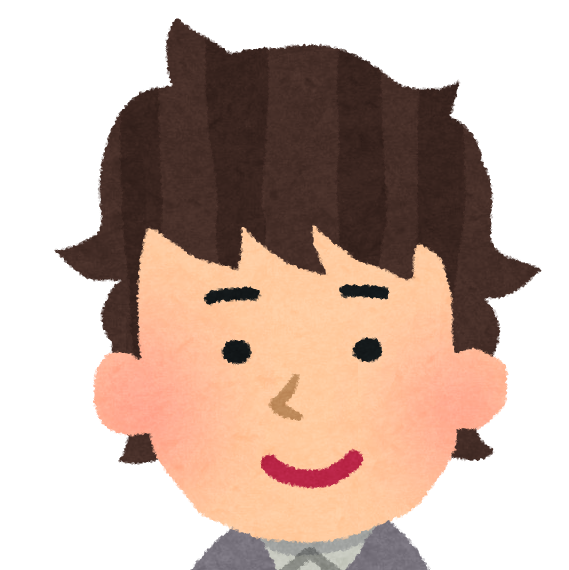
それって、学生のうちから試験を受けられるって話題になってたやつだね!

そう、去年(2019年)くらいから言われてて、いつに始まるのかと思ったらなんと今年(2020年3月)に法改正となったんだよ。

若干今さらな話題になるけど、自分自身あやふやなところが結構あったから今回記事にまとめてみたよ。
3月に施行された建築士法改正から実務経験がどう変わったか、いま一度振り返ってみようと思います。
実務経験の証明は合格後になったので、どの実務経験が証明として使えそうか改めて一緒に確認してみましょう。
令和2年の建築士法改正の概要
3月に施行された建築士法改正の概要は主に以下の4項目に集約されます。詳細は国土交通省住宅局建築指導課のパンフレット(PDF注意!)に書かれています。
- 一級建築士、二級建築士の受験資格の緩和
- 実務経験の範囲が拡大
- 学科試験の免除年数の緩和
- 設計図書保存の範囲拡大
今回のトピックは2つ目の項目のお話になります。そのほかの項目に関しては別の機会に触れたいと思います。
2つ目の内容をざっくりまとめると、
- 実情を踏まえて実務経験の範囲を拡大した
- 実務経験の証明を厳格化した
ということになります。
見直しの背景
一級建築士の受験資格は、構造計算書偽装問題を受けて2008(平成20)年の法改正で一度厳格化されています。
しかし、厳格化したことと受験者が高齢化したことが重なって受験者数が大幅に減ってしまい、今後建築士が十分に確保できないという問題が出てきました。
また、建築物をリノベーションしたり、性能を高めて長寿命化を図ったり、BIMなどのICTを活用したりと、近年建築業務の環境が変化しています。それに合わせて建築士に求められる業務内容も多様化してきました。
これらの時代背景を踏まえて、今回法改正となったようです。

試験のやり方そのものも今後時代に合わせて変わっていくかもしれないね•••。
対象実務の範囲が拡大
建築士試験に必要な実務経験は以下の7項目の実務に拡大しました。
- 建築物の設計に関する実務
- 建築物の工事監理に関する実務
- 建築工事の指導監督に関する実務NEW
- 建築物に関する調査又は評価に関する実務NEW
- 建築工事の施工の技術上の管理に関する実務
- 建築・住宅・都市計画行政に関する実務
- 建築教育・研究・開発及びそのほかの業務
これらのうち、3,4番目の項目については新しく追加された項目で、まったく変わっていないのは2番目の項目だけです。
つまり、ほとんどが今回の改正で何かしら追加・変更になっているわけです。
期待される5つの実務経験
新たに加わった実務経験のうち、大きく需要が期待されるのは5つあります。
それは、
- 構造計算プログラムの開発、BIM部品の作成
- 施工管理(鉄骨工事、鉄筋工事、4号建築物を除く解体工事などの管理経験など)
- 建築確認検査
- 既存建築物の調査・検査
- 建築物に係る研究(査読を経て学会誌等に掲載されるもの)
です。
特に5つ目の研究に関しては、建築大学院生にとっては朗報でしょう。
これまで、実務経験無しで学生のうちに受験できるという事前情報があった頃は、大学教員から試験勉強より研究に専念してほしい•••という意見がありました。
しかし蓋を開けてみると、査読つき論文で実務経験扱いになるということで、きちんと論文を書くための研究もやってくれよと学生に釘を刺せるようになりました。
試験勉強と研究との両立は大変なのは確かですが、後ろめたい気持ちがあるなかで試験勉強するよりは前向きな気持ちで取り組めるのではないでしょうか。
建築学生にとって、インターンシップ以外の選択肢が生まれたこともメリットが大きいです。

エンジ系の学生だったら研究してたらインターンシップなんて行ってられない人も多いと思う。こういう人も試験を受けやすくなったのはいいね。
そのほか、実務経験に該当するか知りたい人は、最新の情報が掲載されている試験元のサイトを確認してみてください。「対象となる実務経験の例示リスト」と検索すると、表でまとめられたPDF資料が出てくると思います。
実務経験の証明は厳格化
実務経験の範囲は拡大した一方で、合格後の実務経験の証明は厳格化されました。
設計者であれば、申告に係る第三者による証明は建築士事務所の管理建築士か所属建築士に限定され、そのほかの場合は原則個人による証明ではなく法人による証明が必要になります。例えば、行政法人の場合は所属長、学校の場合は校長や学部長が証明をする第三者に該当します。
もし、虚偽の申告をした場合は、証明をした建築士が処分を受けることになります。

経歴のごまかしは建築士の品性に欠く行為だから絶対にやめよう!
実務経歴書に書く内容も増加
合格後に証明書と一緒に提出する経歴書も記入項目が増えています。
建築実務の場合を例にすると、対象物件の名称だけでなく住所と業務内容を具体的に書くように求められています。試験元のサイトに記入例が記載されています。
ただ、この記入例のみだと、先ほど挙げたような必ずしも住所に縛られないBIM部品の作成や査読論文の場合はどう書けばいいのか、という疑問が残ります。
令和2年の試験からはこの書式となるため、書き方がよくわからない場合は合格後にあらかじめ試験元に確認しておいたほうが良さそうです。
今後はどうなる?
今回の改正で受験者数が増えるかどうか、今後の動向が気になります。
個人的には、
- 試験の難易度は学生が参入する分、若干上がりそう
- 国の少子高齢化問題は残ったまま
なので、合格者はそれほど変わらず建築士の高齢化問題の解決までには至らないんじゃないかなと考えています。
ともあれ、今回の改正で受験資格を得たのであれば、あとは試験勉強するだけです。早いうちにサラッと合格して建築士になりましょう!







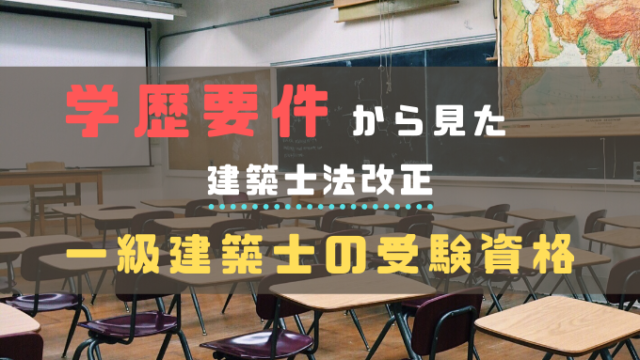
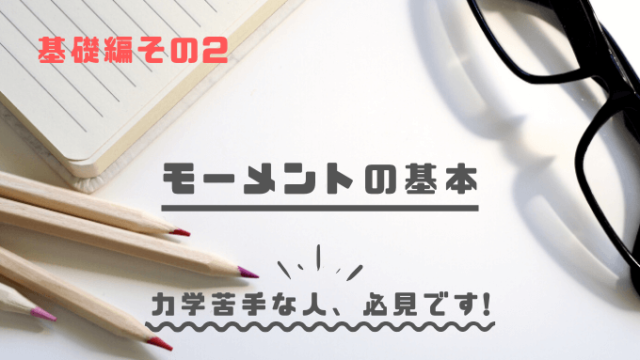

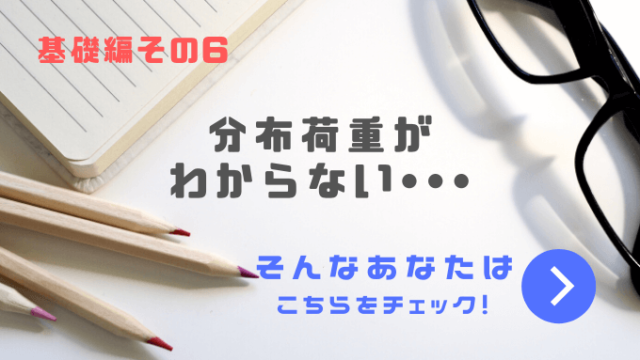
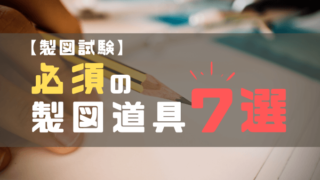
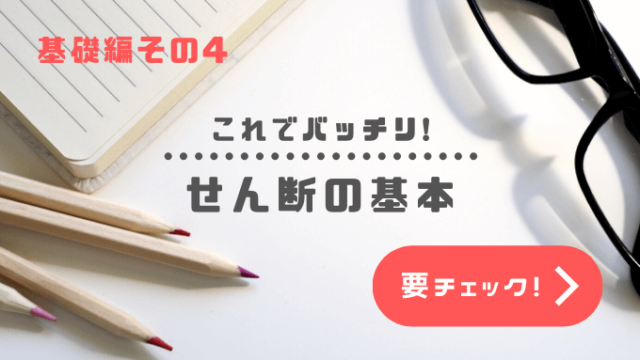




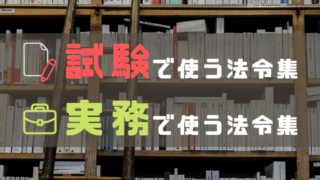
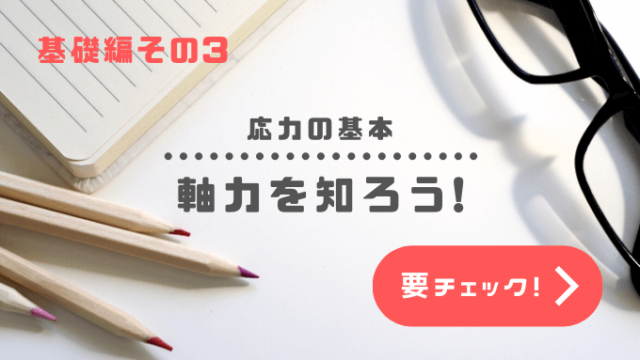





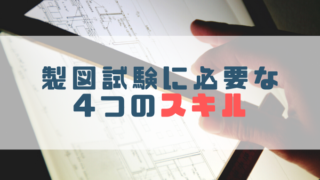
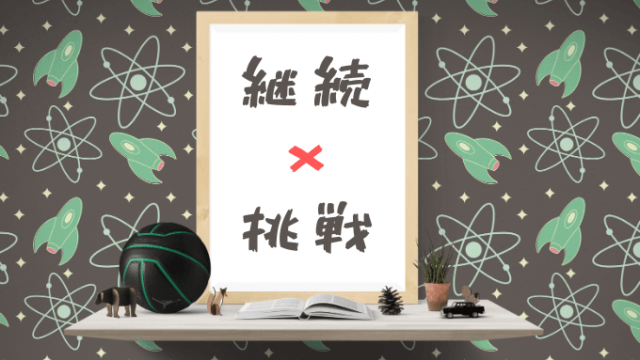

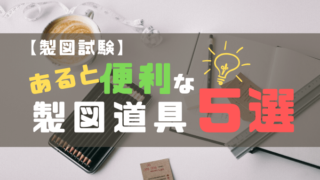
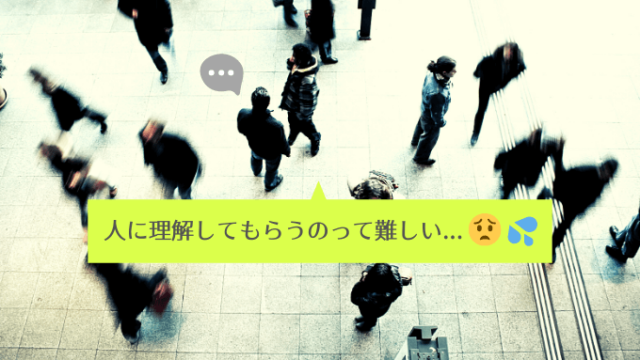


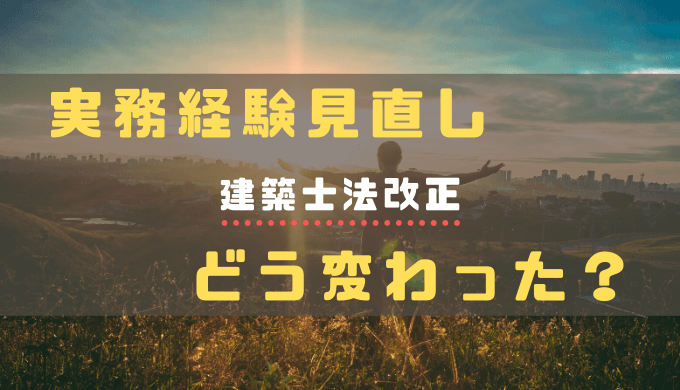
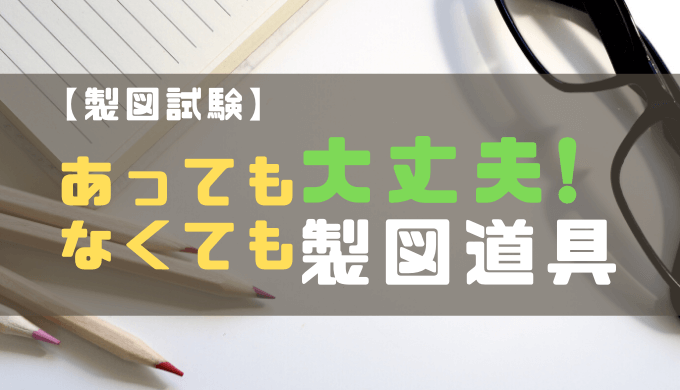
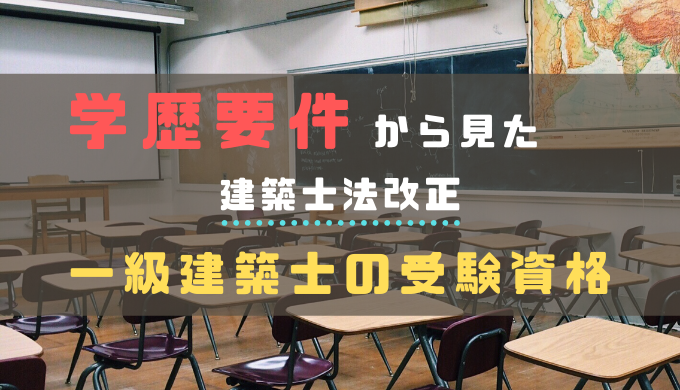
コメント