こんにちは、ゆるカピ(@yurucapi_san)です。
あなたはこんなことに悩んでいませんか?
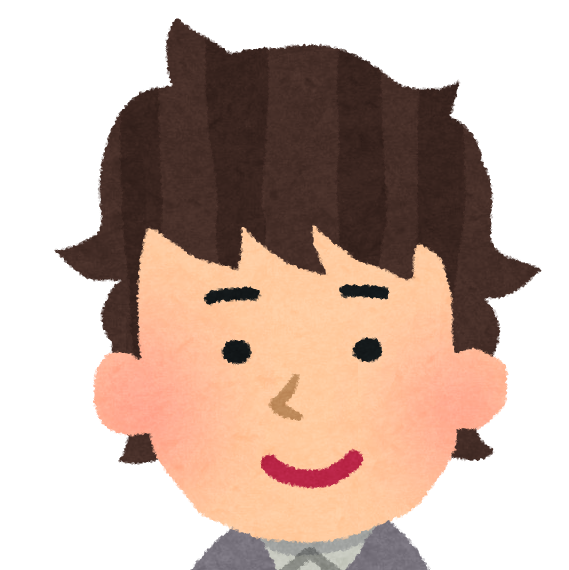
一級建築士の学科試験が終わったけど、製図の勉強しんどそう...。
ベストなタイミングってあるの?
初受験の人にとって、製図の勉強をいつ始めたらいいのか、よくわかりませんよね。
- 学科の勉強しながら製図の勉強もちょっとやるのがいい?
- 大変てよく聞くけど、1年くらいかけないと厳しい?
資格学校にも1年以上の長期コースがあったり、学科の合間にちょっとしたエスキスを描かせたりします。
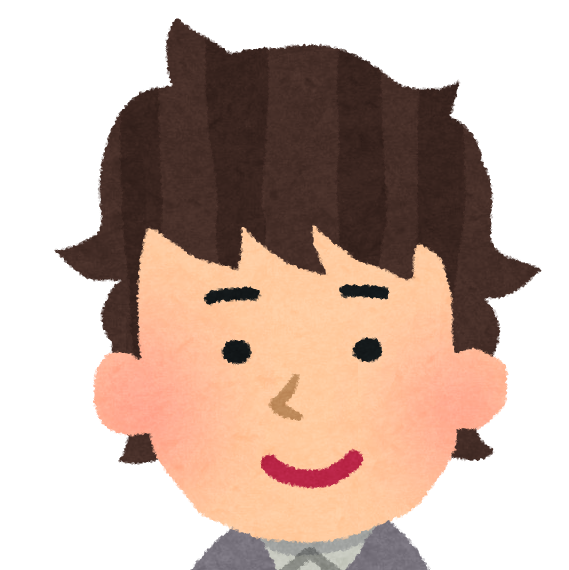
正直、どのタイミングで製図の勉強をしたらいいのかよくわからない。
ひょっとしたらこんなことを悩んでいるかもしれません。
私自身、一級建築士試験はストレート合格しています。なので、学科試験合格後の7月後半から製図試験の10月までの約2.5ヶ月で合格可能です。
つまり、結論を言ってしまうと、製図の勉強は7月後半〜8月前半あたりがベストです。
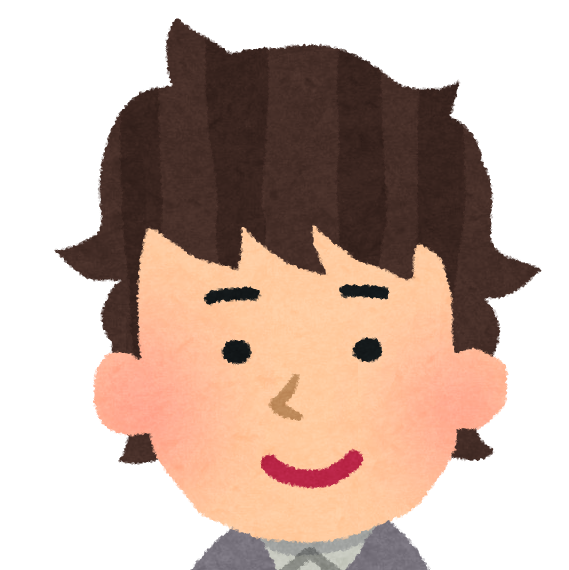
いやいや、もともと製図得意だったんでしょ?
と思うかもしれませんが、大学3年以降、全くと言っていいほど手描きの図面に触れていませんし、構造系出身というのもあって、決して得意とは言えないと思います。
それでも合格できたのは、
短期集中で鬼作業&試行錯誤の繰り返しを続けたから
だと思っています。
今回は、
- なぜ短期集中がいいのか
- 学習計画を立てる時に気をつけること
について解説したいと思います。
製図勉強は惰性では続かない

そもそも、製図勉強はしなくても人は死にません。もちろん、食事と睡眠はとらないと死んでしまいます。
しなくてもいいことをわざわざするのは、それなりにエネルギーが必要だということです。
ただ、これについては学科試験勉強と一緒。違いは桁違いに作業がしんどい、ということに尽きます。
製図勉強を始める前に、
- かなりの時間を投入する必要がある
- 学科試験以上にモチベーションを維持するのが難しい
ということは念頭に置いておきましょう。
かなりの時間を投入する必要がある
エスキスと作図の時間を分けたとしても、それぞれ2、3時間はかかります。
平日の仕事終わりのくたくたの状態でこの作業をやるのはなかなか酷です。仕事が22時終わりなんてことになったら、深夜の睡眠時間を削りながらやる必要も出てきます。
もちろん、休日は土日両方とも製図勉強にフルコミット。はっきり言って、休む時間は睡眠時間と移動時間、わずかな食事のひとときのみ、です。
なので、それなりの覚悟で製図勉強をしないといけません。

とてもじゃないけど、惰性でやれる作業じゃないよ。
モチベーションの維持に苦労する
最初のうちは、覚えることがいっぱいでひたすら作業をこなしていく日々になります。
ここが序盤の山ですね。
次の山場は9月に入ってから。
- 作図演習をこなしてるのに、なかなか描くスピードが速くならない
- エスキスがうまいこといかない
本試験まで残すところ1ヶ月くらいしかないのにやばい、という危機感と不安感でいっぱいになります。

ここで振り返り作業と試行錯誤の繰り返しがきちんとできるかが重要だね。
この間、モチベーションの波は大きく変動するので、維持するのは想像以上に大変です。
なので、モチベーションは当てにしないのがいいでしょう。後述しますが、自分の心のモチベーション以外で、続ける方法を見つけるのがよいです。
製図学習は短期集中で鬼作業がベスト
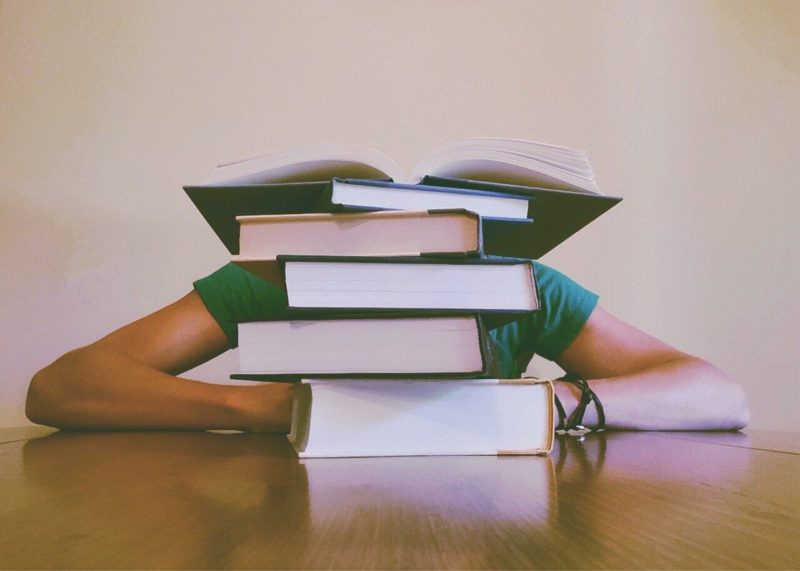
製図勉強は短期集中でやるには、めちゃくちゃハードな作業内容です。
こんなことを書くと、
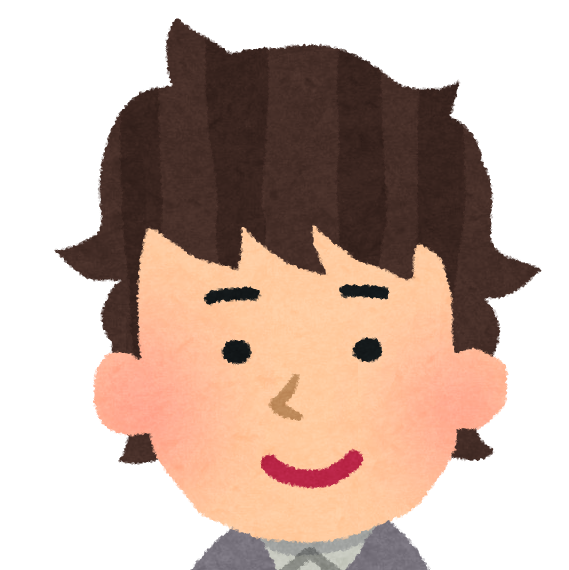
だったら、今年の受験は諦めて1年かけて製図の勉強するのがいいんじゃないの?
と思うかもしれません。
でも、考えてみてください。
製図勉強は長期間やろうが、短期集中でやろうが、やることは一緒です。
おまけに、エスキス2時間、作図3時間を細分化しても、全然実践力が身につきません。単にダラダラ時間をかけて作業することになるだけです。

例えば、
- 柱だけ書くのに5分
- 壁を描くのに20分
- 断面図に30分
みたいなのを意識してやるのはいいけど、それを何日もかけてやるのはすごく勉強の効率が悪いと思う。
なるべく、通しでやったほうが実践的でおすすめだよ。
それなら、
- 短期集中で鬼作業(毎日空いている時間はすべて製図勉強に投入)
- フィードバックをもらいながら、ひたすら試行錯誤
のほうがはるかに効率的です。
結果的に早期で受かる可能性が高まるので、体力的、精神的負担も少なく済むはずです。

しんどい作業だからこそ、短期集中でサクッと終わらせることが大事だね。
7月後半〜8月前半に勉強を開始すべき理由

じゃあ、いつやるの?今でしょ!
•••と言いたいところですが、諸事情あって今すぐできない人もいると思いますし、ベストな時期というのもあるので、今すぐ製図勉強を始めようとは言いません。
2020年からは建築士法改正で、学科試験合格後に製図試験を受験可能な年数が5年に伸びました。5年間の猶予期間の中で3回チャンスが与えられているので、戦略的に今年は受けない、と考えている受験生もいると思います。
建築士法改正については、以下の記事が参考になります。
このことも加味してもおすすめな勉強開始のタイミングは、ずばり7月後半〜8月前半の時期です。
その理由は以下のとおり。
- 毎年製図試験の課題発表があるタイミングが7月後半あたり
- 課題発表に合わせて資格学校の短期コースが始まる
- 製図試験に関する情報が増える
- 製図試験を一緒に勉強する仲間が増える
製図試験の課題発表は毎年学科試験の2日前の金曜日に発表されます(2020年は学科試験の時期を早めた関係でタイミングがずれています)。
これに連動して、資格学校の短期コースが始まり、試験に関する情報が集まりやすくなって、製図試験の勉強する人も一気に増えます。
なので、製図勉強を始めるベストタイミングは、7月第3週目あたりから8月第1週あたりになるわけです。
作図やエスキスを学ぶのも大事ですが、結局、試験は情報戦だったりします。
情報が集まりやすい7月後半から勉強を始めたほうが、無駄な労力を割かずに済みますよ。

一緒に勉強する仲間も大勢いるからモチベーションを維持しやすいよ。
学習計画を立てる時に気をつけるポイント

最後に、学習計画を立てる際に気をつけないといけないポイントについてお伝えします。
それは、
- 期限を決める
- モチベーションは当てにしない
- 1人で勉強しない
の3点です。
期限を決める
学習計画、と言ってる以上、期限を決めましょう。
まずはストレート合格を目指して、
- 7月後半 :製図勉強を開始
- 8月 :ひたすら作図量をこなす&エスキスに慣れる
- 9月前半 :作図時間2時間半を目指す
- 9月後半 :細かな試行錯誤、質の向上を目指す
- 10月第1週:全体の復習、本試験問題予想を立てる
という具合に細分化して、小目標を立てていくのがおすすめです。勉強を進めるごとに適宜計画の見直しをしていきましょう。
モチベーションは当てにしない
自分の心のモチベーションほど当てにならないものはありません。
例えば、明日は早起きしようと思っていても、いざ翌日になると、もうちょっと寝てもいいかなと気持ちが緩んでしまって、結果早起きできないという経験はありませんか?
こういう時は、
- 目覚まし時計をあらかじめセットしておく
- 早朝に絶対やることをあらかじめ決めておく
ということをしておくいいでしょう。
なにかを継続させるためには、自分の感情に左右されない外部的要因を持っておくことが効果的です。
次に挙げる「1人で勉強しない」も、そのうちの1つです。

同じ会社の同僚で製図試験を受ける人がいたらラッキー。挫折しないためにも、一緒に勉強するのがおすすめだよ。
1人で勉強しない
口酸っぱく言っていますが、製図勉強は想像以上に気力と体力が必要なしんどい作業です。
相当自身があるかストイックな性格でない限り、1人で勉強するのは難しいのが現実です。
ひと昔前までは、ほかの人と勉強するためには資格学校に通う必要がありました。今はSNSやZoomによる講義などを通してオンラインでほかの人とつながりながら勉強することができます。
経済的にあまり余裕がないけど、1人で勉強するのはしんどいという人はぜひオンラインでの交流を図ってみてはいかがでしょうか。
まとめ:まずは少しでも行動しよう!
学科試験が終わると、気持ちがスッと抜け落ちがちです。実際、学科試験後の1週間くらいは試験モードから一時休止モードになると思います。
なんとなく気持ちが乗らないな、と感じている人は、
- とりあえず製図道具をそろえる
- 資格学校の講師やSNSで教えてくれる人に相談する
で、気持ちを製図試験モードに切り替えていきましょう。
諸事情あって、すぐには試験を受けられない人は、
- 周囲の人やSNSに今後の決意表明をする
- ノートに決意表明を書き出してみる(SNSにアップするのはちょっと...という人向け)
あたりをやっておくのがおすすめです。こちらについても、製図道具を先にそろえておくのもいいでしょう。
少しずつ行動に移していきましょう!
以下におすすめの製図道具を紹介した記事を貼っておきます。参考にどうぞ。
それでは、また。



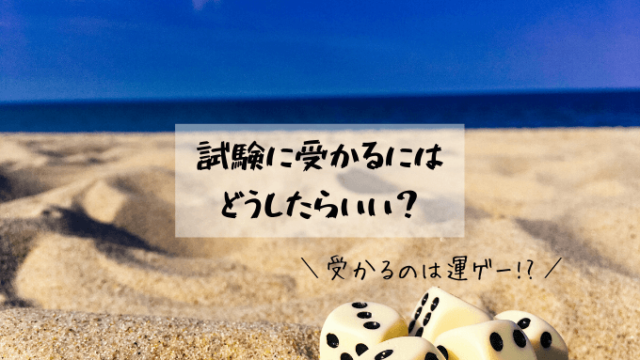



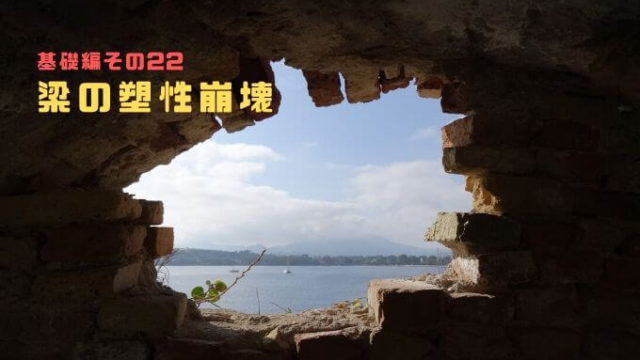
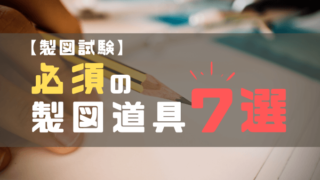



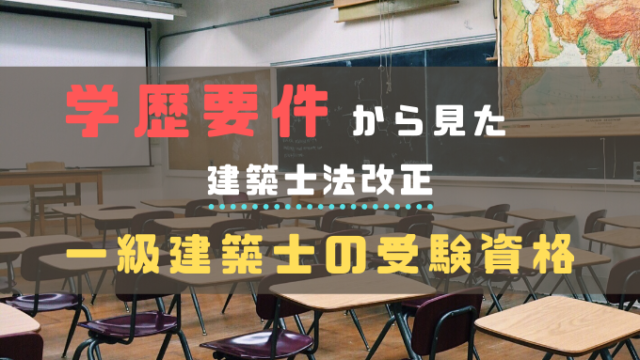
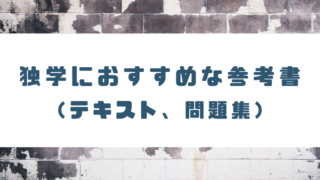
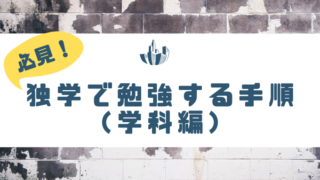

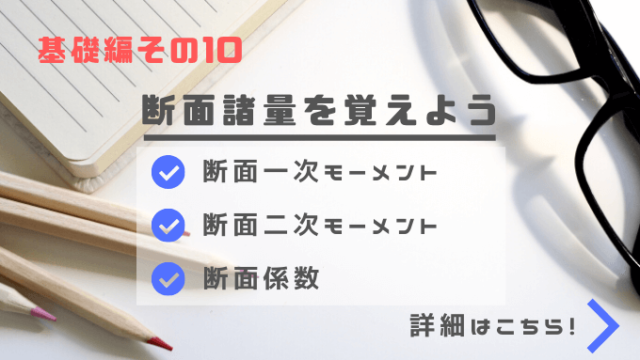
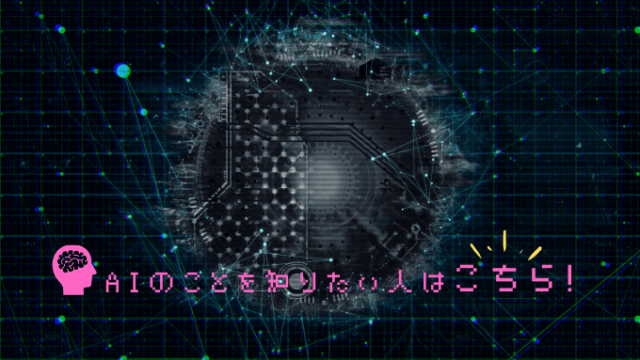

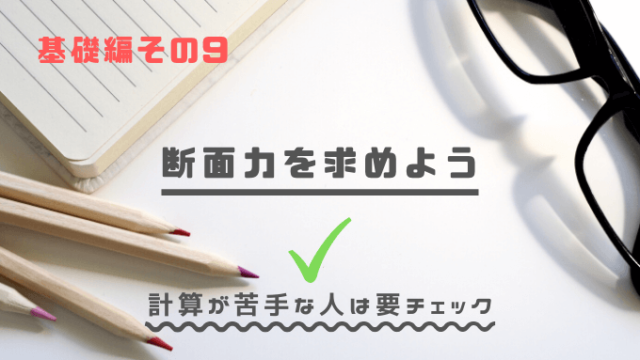




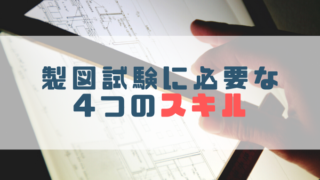

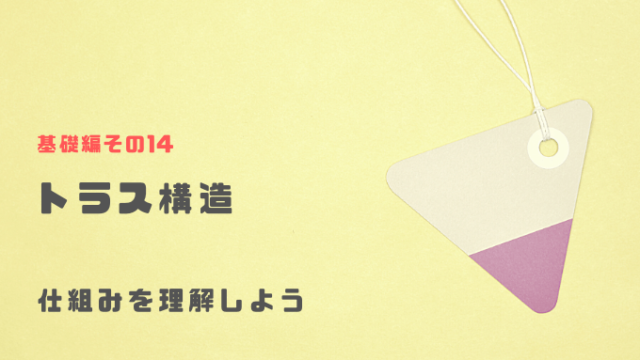
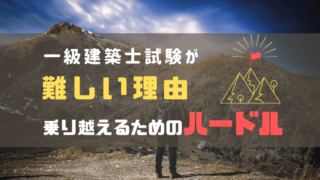





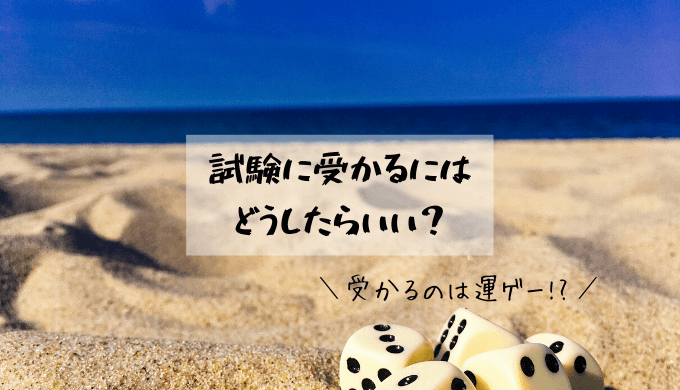
コメント