こんにちは、ゆるカピです。
今回は「部下の心が折れる前に読む本」のレビュー感想をお伝えします。
↓紹介する本はこちら↓
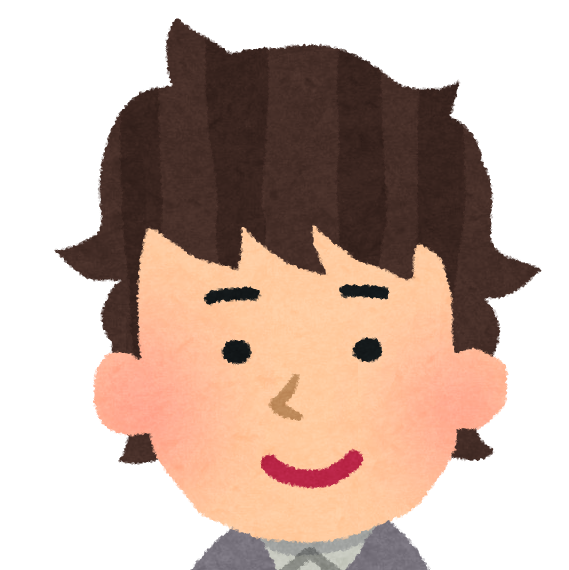
へえ、珍しいね。いくつか質問してもいいかな?
読んだきっかけは?
たまたまメルカリで読みたい本を探していた時に、おすすめの本として出品されていて、タイトルが気になったから読んでみた感じです。
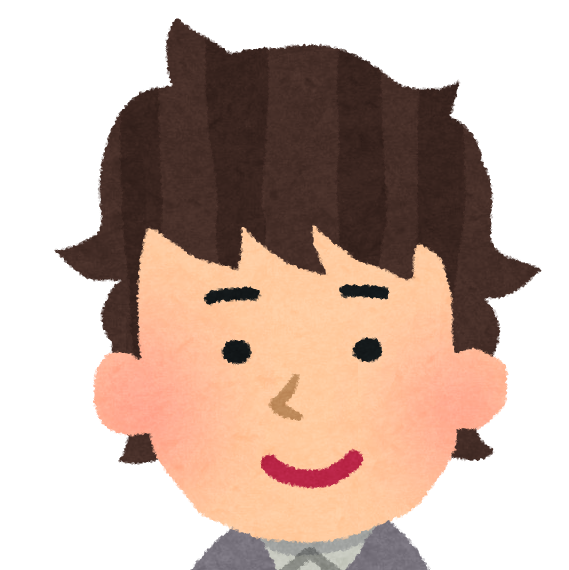
CDのジャケ買いみたいな感じか〜。

あと、自分自身、過去にメンタル面でつらい時期があったから、ちょっと気になったんだよね。
どんな話が書いてあるの?
ざっくり3行でまとめると、
- 現代人にはメンタルヘルス対策が必須
- 社員がやめない会社にするには4つのケアが重要
- 産業医をもっと活用しよう
という内容です。
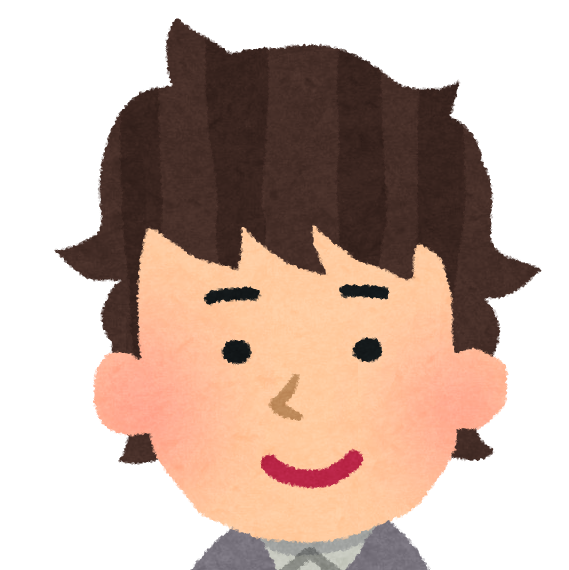
4つのケアか〜。そっち方面の専門じゃないから専門用語とか出てきたらわかんなくなっちゃうなあ。

この本には全然小難しい用語は出てこないから、サクッと読めるから安心して大丈夫だよ。
どんな人におすすめ?
著者は企業の管理職、人事・労務担当者、経営者にぜひ読んでほしいということでこの本を書いたそうです。
しかし、実際読んでみた感想としては、この本は働く人なら誰でもおすすめできる本です。
理由は以下のとおり。
- 部下の立場の人も将来的に上司の立場を経験する
- メンタルヘルス対策を知っていれば自己防衛になる
- 就活や転職の時、会社選びのひとつの指標になる

メンタルヘルスケアのことを知っているだけで、いろいろと役に立つよ。
いつもと違うテーマ?
今回はいつもの一級建築士試験の話題とは違ったテーマの記事を書いています。
よく、建築業界は長時間労働でブラックな業界だと言われます。
働き方改革が提唱されて数年が経過していますが、業界には、たくさん働くのが当然だと考えている人が少なくありません。
自慢するつもりはありませんが、私自身、過去に月100時間超の残業時間が2ヶ月以上続いた経験があります。
これくらい残業してしまうと、心身ともに疲労困憊で、まともに頭が働かなくなってしまいます。
同じように残業地獄で苦しんでいる人、メンタルヘルス不調に陥っている人にはぜひ読んでほしいなと思います。
本の内容はどんな流れになっている?
本の中身は、まとめるとこんな感じです。
- 部下のメンタルヘルス不調が続くとどうなるか(第1章)
- メンタルヘルス不調の原因はなにか(第2章)
- メンタルヘルス不調とストレスの関係(第3章)
- どんな時にメンタルヘルス不調になりやすいか(第4章)
- メンタルヘルスケアの対策方法(第5章)
- メンタルヘルス対策の企業の事例紹介(第6章)
- 著者の考える今後の展望(第7章)
前半4章分がメンタルヘルスの原因編、対策編は5章と6章にまとめられています。対策を手っ取り早く知りたい人は5章から読むのもいいでしょう。

各章の章末にまとめが載っているから、そこだけまず読んでみて気になった章から読むという方法もあるよ。
本の内容は建築業界にどう関連するの?
それでは、この本のテーマになっているメンタルヘルスの話は建築業界にどう関係しているのでしょうか。
この本では、労働生産人口の減少に伴って採用のハードルが上がっているため、メンタルヘルス不調で休職、離職する人が出ると、企業としても損失が大きいとしています。
建築業界では、現場の職人が足りないという話はよく耳にします。実際、人手が不足していて年々労務単価が上がっています。
大卒の離職率もおよそ3割程度なので決して低い数字ではないことがわかります。
設計業の場合、新卒採用と中途採用を合わせた人の数と同じくらい、毎年のように人がやめていくのが実情としてあります。
著者は、年収500万円の部下1人が1年間休職した時の損失額は約1,500万円だと主張しています。
離職した場合もまたいちから教育しなおさないといけなかったり、即戦力になる人材が集まらなかったりするので、同じか、それ以上の損失額となることでしょう。
冒頭でもお伝えしたとおり、建築業界は長時間労働で有名な業界です。
長時間労働を続けているとメンタルヘルス不調に陥ってしまうリスクが高まります。
離職率を下げるためにも、社員の健康を保つためにも、建築業界にメンタルヘルス対策は必須といえます。
部下の立場ならここは読んでおきたい
もし、あなたがこれから新社会人になって上司のもとで働くのであれば、特に読んでおいてほしいところがあります。
それは、第2章のメンタルヘルス不調増加の原因③と⑤です。
- ③中間管理職のプレイング・マネージャー化
- ⑤上司からの無意識のハラスメント
ほかの3つの内容も重要なのですが、ある程度マスメディアなどで言われているなので、理解のある人が多い印象です。
しかし、上の2つについては、実際設計の仕事をしていて苦労したと感じた内容でした。
もし、あなたが部下の立場だったらこんな経験はないでしょうか。
- 教えてほしいのに上司が忙しくてなかなか相談できない
- イヤというほどではないけどちょっと不快なことを言われた
今の職場の上司にあたる人は、設計もバリバリこなしながら部下のマネジメントもするプレイング・マネージャーになっていることが多く、想像以上にストレスフルな毎日を送っています。
この時、③と⑤が組み合わさって、部下がメンタルヘルス不調に陥ってしまう可能性は十分考えられます。
このような状況に備えるためにも、ぜひ目を通しておきましょう。
仕事や実生活に生かせることは?
この本を通して仕事や実生活に生かせることは以下の3つです。
- 自分の心身の不調がわかる
- クラッシャー上司の対処を考えるきっかけになる
- 会社のメンタルヘルス対策をうまく活用できる

どれも大切なことだね。
自分の心身の不調がわかる
意外に思うかもしれませんが、自分ひとりではなかなか自分の不調に気づけないものです。
なんだか身体の調子が悪いなと感じたら、メンタルヘルス不調に陥っていたという可能性も十分にあります。
今まで気にかけていなかったことに気づける良いきっかけになるでしょう。
クラッシャー上司の対処を考えるきっかけになる
世の中には部下を精神的に追い詰めるクラッシャー上司と呼ばれる人たちがいます。(出典:松崎一葉『クラッシャー上司 平気で部下を追い詰める人たち』PHP研究所)
部下は上司を選べないので、仕事をしているとこのような面倒なタイプの人と関わってしまうと大変です。
このタイプに絡まれたらどうするかというと、
- いったん距離をとる
- 心が落ち着いたら相手の言動を冷静に見る
- 対処方法を考え、自分にできることにのみ集中する
とするのがいいと思います。
メンタルヘルス不調に陥っていると、頭のなかがモヤモヤして、なかなか冷静に対処できません。
この本を通してメンタルヘルス対策を知っていれば、対処方法もすぐに浮かんでくると思います。
会社のメンタルヘルス対策をうまく利用する
メンタルヘルス対策の考え方を知っていれば、会社が用意している産業医面談などを積極的に活用するメリットも見えてくるでしょう。
会社や上司の不満を愚痴っているのはもったいないので、産業医に相談して実際に行動してみるのもいいと思います。
前向きな産業医であれば有効な対応策を教えてくれるはずです。
まとめ
「部下の心が折れる前に読む本」は働く人全員におすすめな本です。
きっと役に立つと思うので、一度手にとって読んでみてはいかがでしょうか。


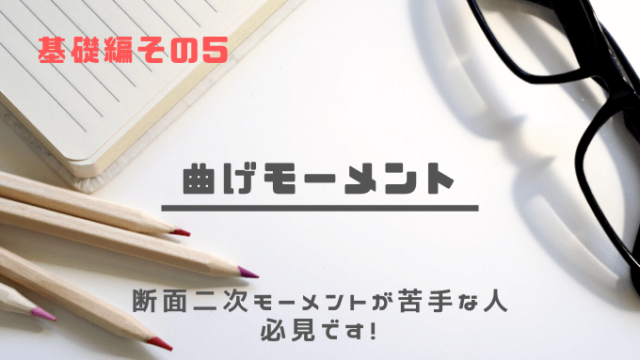
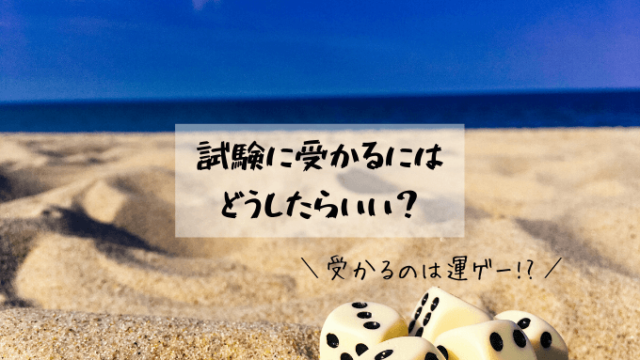
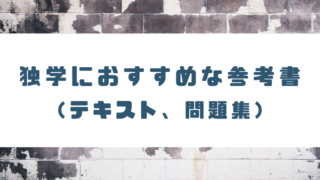
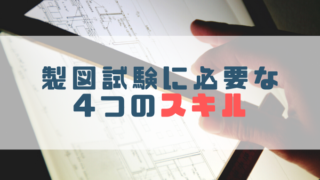



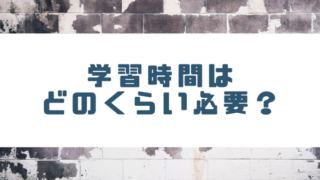
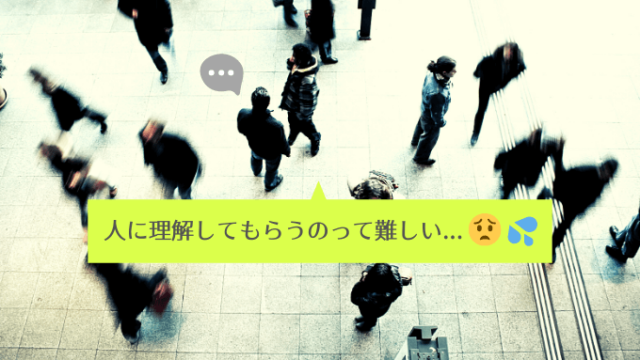






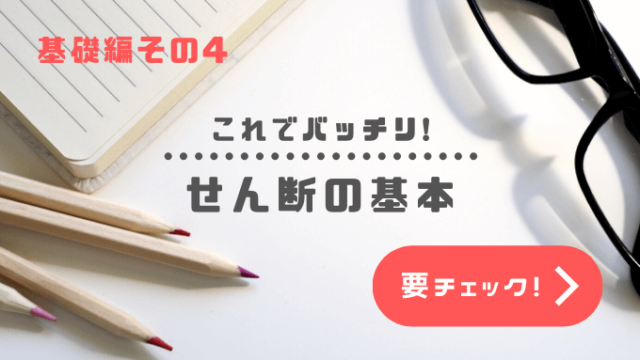

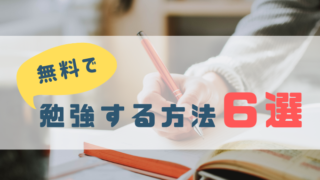





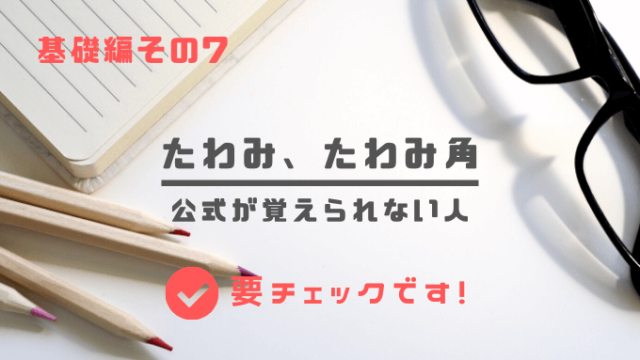
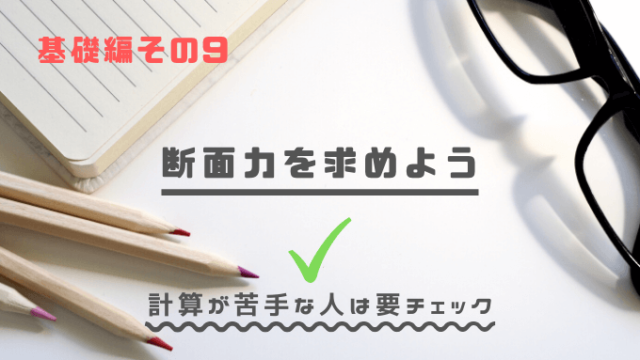

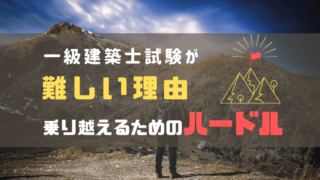
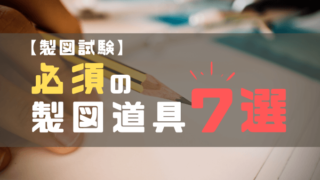
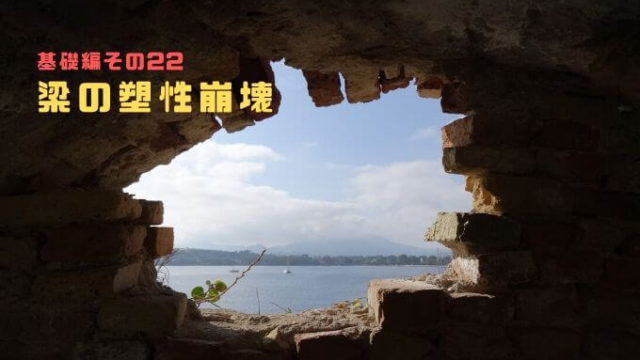
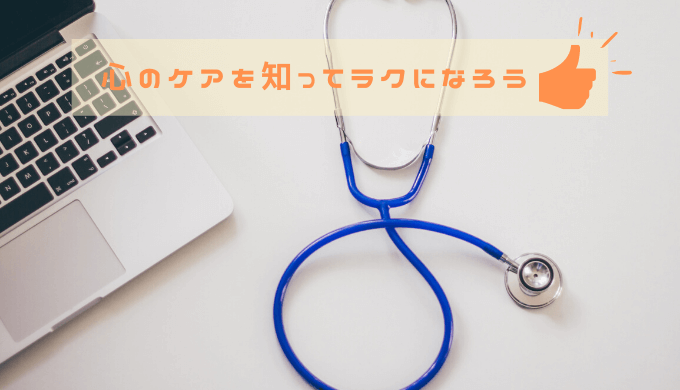

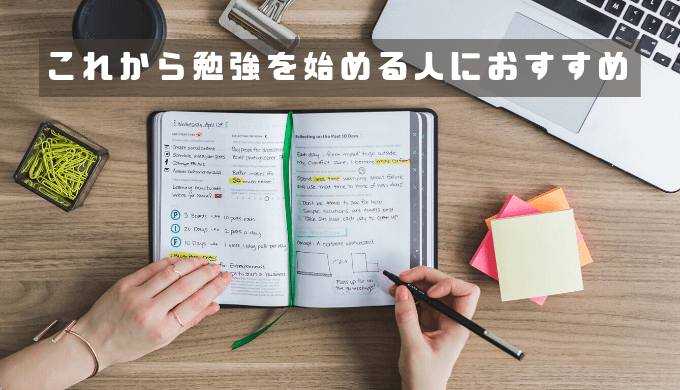
コメント